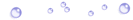一国の王というのは、楽じゃない。
特に外国育ちの女王ともなれば、国内の敵も計り知れない。
国内外で持ち上がる問題を平和的に処理し、時代に疲弊しきった国民を未来へと導く。
果てしなく困難な道のりを、それでもエステルはなんとかこなしてはいた。
毎日が、辟易するような戦いの連続だった。
そうしていつの間にか、エステルがアルビオン女王の座について、5年が経っていた ――― 。
この日も、怒涛のような1日を終え、エステルは儀式用ではない自分のベッドに横になった。
3年ほど前のあの日のことをぼんやりと思い出す。
アルビオン女王としての日々が、ようやく形になりだしたあの頃。
カインとの戦いを前に、アベルは寝室に忍び込んできた。
悲愴な決心に、彼の顔は硬かった……。
公務に疲れきっていたエステルは最初、その気配を気のせいかと思った。
女王が眠る部屋の警備は厳しく、何よりも、ここにいるはずがないひとの気配だったから。
けれど、あまりにも慣れ親しみ、探していたその気配は消える様子がない。
おそるおそる振り返ったエステルは、息を呑む。
「お久し振りです」
(神父さま……?)
数歩離れた壁際に、神父アベルが立っていた。
あまりのことに、言葉を探すことすらできなかった。
どうして、ここにアベルがいるのだろう?
(幻覚……?)
逢いたい気持ちが募りすぎて、幻を見ているのだろうか。
幻は、こんなにもはっきりと気配を残すものだろうか……?
目の前のアベルは、固まるエステルに優しく笑みを見せた。
「どうしたんです? そんな驚いた顔をして」
「 ――― 本当、なの?」
「? 本当、と言いますと?」
「本物の、神父さま、なんですか?」
眉間にしわを寄せるアベル。
「ずっとそのつもりでいたんですけど? 何か、手違いでも?」
「いえ、そういうわけじゃ、ないんですけど……」
その表情とどこかずれた返答は、まさしくアベルのものだ。
「戦いは、どうなったんですの? もう、終わったんですか……?」
エステルとは違う方法で、戦いの道を選んだアベル。
いまこの場にいるのは、それに何らかの形で終止符が打たれたからなのだろうか。
アベルは、眼差しを一瞬揺らがせた。
「いいえ。終わったわけではありません」
「まだ、続くんですね」
期待を抱いてしまったからこそ、落胆は大きく胸に落ちた。
「でも、もう終わります」
「え……?」
きっぱりと断言したアベルに、エステルは戸惑う。
アベルの戦いの果てには、カインがいることを、エステルは知っている。
カインとの戦いが、壮絶なものになるだろうことも。
それを、こんなにもあっさり終わると言いきれるものなのだろうか。
自分を見下ろすアベルの眼差しは、あまりにも深かった。
そこに、彼の覚悟の強さを見つける。
胸の中に、不安が冷たい雫を落とした。
「神父さま、……戻ってきてくださるんですよね?」
エステルの問いかけに、アベルの眉根がほんの一瞬、ごく僅かひるんだ。
「まさか、戻らないつもりなんじゃ……」
「そんなわけないじゃないですか」
――― そんな答えを待っていたのに、アベルは硬い表情のまま、何も言ってはくれなかった。
エステルはアベルの袖口を掴んだ。
「神父さま……!」
「どうなるかは、判りません。判らないんです」
いつもの、すぐに冗談めかすアベルの気配を探す。
だが、アベルの表情のどこにも、からかいの色は見出せなかった。
エステルは、怖くなる。
夜遅く突然寝室に忍んできて、思いつめた表情を崩さないアベル。
それはまるで、今生の別れを告げに来たようで……。
ぞっとした。
「いやです……!」
袖口を掴む指先は、白く震えている。エステルは知らず全身に力が入っていることに気付かない。
「そんなこと、おっしゃらないでください……!」
アベルは、けれど首を静かに横に振る。
「最後に、どうしてもエステルさんの顔を見ておきたくて」
「やめてください!」
声を荒げてはいけない。隣室には女官が控えているのだ。
それすらも、エステルには瑣末事に思えた。
アベルが最後と言う。
最後に、エステルの顔を見に来たと。
「最後だなんておっしゃらないで。命を落とすことを前提に……、逢いに来ないでください! 神父さまおひとりで、わたしを置いておひとりで先に逝こうとするなんて、やめてください」
あまりのことに身が震える。
ふざけたことを言って。そう言い捨てられないのは、アベルの覚悟が眼差しから、表情から、全身から伝わってくるからだ。
「優しいことを、言ってくれるんですね」
淡い雪のような微笑みに、アベルは言葉を乗せる。
「このまま、自分の決心から目をそらしたくなってしまいます」
( ――― そらして下さい)
できることなら。
エステルは胸の内の叫びを、けれど声にすることができなかった。
簡単に願いを口にできるほど、エステルはアベルのことを知らない小娘ではない。
政治的にも、純粋な気持ちの面でも。
アベルはこんなときに、本音ばかりを言ってくる。
どうしてこういうときにこそ、その場しのぎでもいい、取り繕った言葉をかけてくれないのだろう?
どうして自分は、何も知らない小娘じゃないのだろう!
(そうすれば、すべて捨てて神父さまと一緒にいられるのに!)
「!?」
たまらず両手で顔を覆ったエステルは、強い力で抱きしめられた。
「こういうときくらい、せめて、もっと甘えてくださいよ」
愛しむように、アベルはエステルの髪に頬を埋める。
「いろんなしがらみに縛られて、自分の気持ちも、わがままも、いつも我慢して、みんなのことばかり優先して。こんなんじゃ、エステルさん潰れちゃいますよ、だめですよ頑張りすぎちゃ」
アベルの言葉は優しすぎて、まるで最後の伝言にも聞こえる。
そんなのは、欲しくなかった、聞きたくない。
けれど、ひと言でも多く、 ――― アベルの声を聞いていたい。
「エステルさんのわがままも、聞いてみたいんですよ」
いつもみたいに、的外れな素をさらして欲しい。
苦しそうに言葉を吐くことで、覚悟の深さをエステルに思い知らせていることに、気付いているのだろうか?
それでも、彼の声は愛しくてたまらない。
アベルはエステルを抱く腕に力を込めた。
言葉にできない想いが、そこから溢れる。
エステルも、アベルの背中にやる腕に想いをこめた。
夜の静けさに溶けこむように、ふたりはお互いを抱きしめあう。
どれくらいの時間が経ったろう。
ゆっくりと、アベルは腕を開いた。
救いを求めるように、エステルを見つめる。
思いつめたその眼差しには、深い覚悟と決意が見える。
近付くアベルの顔 ――― 、しかしエステルは唇が触れ合う直前、すっと頬を傾け避けた。
アベルの喉が音を立てる。
「 ――― すみません」
ひどく傷付いた気持ちを、懸命に隠そうとする声。
かぶさるように、エステルは言葉をほとばしらせる。
「違うの」
アベルは、悔いるように目を伏せていた。まるで、自分自身を責めるかのように、眉間にしわさえ寄せて。
「あたし、待っていたい」
アベルの眼が、問うように揺れる。
「さよならは嫌。おかえりなさいっていうキスでないと。このままなんて……神父さま勝手すぎる、ひどいわ、ずるい! 勝手に、わたしから生きる希望を、奪い取らないでください……!」
はっとするアベル。
アベルの僧衣を握り締めるエステルは、必死だった。
生きている。ただそれだけで、前へ進む力となる。
「ひとりにしないで……!」
生き残って欲しいのに。
生きるための、帰ってくるための戦いでなければならないのに。
どんなに懇願しても、自分の言葉はアベルの胸を通り過ぎるばかりだ。
エステルは、自分の無力さが悔しい。
非力な自分に、アベルの胸を力なく叩く。
アベルはそっと、エステルの背中に腕を添えた。
本当に小さな、背中だ。
胸底から、言いようもない熱い吐息がこみ上げてきた。
決して失ってはならないものが、ここにある ――― !
エステルは、息もできないほど強く、強く抱きしめられた。
「エステルさんのところに、帰ってきてもいいんですか?」
「当たり前でしょう……! あたし、ずっと、ずっとずっと待ってますから!」
「 ――― うん」
「おばあちゃんになっても、待ってるから。あたし、それまでは、……あたしキスを、守るわ。誰ともキスは、しない」
息を呑むような沈黙を返すアベル。だが、エステルは微笑みすら浮かべる。
「キスを知らない女王だって嘲われたら、いやでしょう? ね、だから必ず、戻ってきて」
アルビオン女王エスター。
立場上、彼女にさまざまな縁談が持ち上がっていることを、もちろんアベルは知っている。
それでも、待ってくれると言う。
キスを守るということは、誰かと結婚をしても、心はアベルに奉げるという意味に他ならない。
渇ききった荒野に、潤いの雨が降る思いだった。
待ってくれているひとがいるということが、こんなにも心強いものだとは ――― !
ひとりきりの戦いなんかじゃない。
アベルは、頬擦りをするようにエステルを抱きしめ続けた。
時間が許す限り、きりのつかない気持ちにふんぎりをつけられるまで。
それは長い長い、時間にも思えた ――― 。
あれから、もう3年が経ってしまっている。
アベルがなかなか現れない間に、いろんなことがあった。
貴族と市民たち、そして長生種たちとの衝突。そして ――― どれだけかわしていても現実的に進んでゆく、某貴族との縁談。
なんとか乗りきっていると思う。
ちゃんと、それなりにはやれていると、思う……。
ただひとつだけ、たったひとつだけ、足りないけれど……。
――― 眠りに落ちそうになる直前、エステルはかすかな物音をとらえた。
小枝が窓を叩いたような、そんな静かな物音。
エステルは軽く身を起こした。
確かな気配があるわけではないけれど、無意識に目は、探すことを覚えてしまっている。
これまで何度、夜中の物音にアベルを探しただろう。それは風の音だったり、遠くの部屋からの話し声だったり。どれもが欲しいものではなくどれもが、落胆をばかり返してきた。
今度こそと思いをこめて求めるひと影を探す。3年も続けていれば、胸の底に溜まってゆく落胆は、硬い澱のようになり、エステルの希望を内側から蝕んでゆく。
それでも。 ――― それでも、確かめずにはいられなかった。
アベルが帰ってきたと、この目で確認せずにはいられない。
おそるおそる、エステルはベッドの向こうへと意識をはわせる。
――― 視界が、一瞬すべてを見失った。
全身に、空虚な嵐が吹きぬけるような衝撃。
同時に、身体の内側が激しく沸騰するような侵蝕が。
すべての意識は、一点にだけ集中していた。
天蓋からのカーテンの向こうに、静かにたたずむひと影が、ひとつ。
胸の内のすべてが、溶けるように崩れてゆく。
ただ涙だけが、溢れてくる。
ふたりはじっと見つめあう。エステルの中に言葉はなく、感激ばかりが想いをいっぱいにさせていた。
「 ――― ただいま。エステルさん」
緊張がにじむ声。彼はエステルの左手薬指に眼差しを投げながら、慎重に近付いてくる。
「もう、遅すぎましたか?」
首を振るエステル。
彼はほんのり表情をやわらがせる。
何度も、夢を見た。
こうしてふと目覚めると、そこにアベルがいるという夢を。
それはいつも唐突に目覚めを迎えて、はかない喜びと寂しさに胸を震わせていた。
いま目の前にいるのは、 ――― 夢じゃない。本物の、真実のアベル・ナイトロードだ。
生きて、動いている。
闇に慣れたエステルの目は、歩み寄るアベルの姿をはっきりととらえている。
ベッドに身を起こしたまま動けないエステルは、ただもうひたすらにアベルを見上げることしかできなかった。
ベッドは背が高い。
アベルはベッドに軽く腰掛けながら、エステルの頬に手を伸ばした。
「こんなにも遅くなってしまって、すみませんでした」
言って、エステルの涙を指の背で拭う。
その腕を、エステルは抱きしめた。
アベルの腕だ。
大きな吐息が、唇から洩れた。
いままで判らなかった。
どれだけ自分が気を張っていて、無理を重ねていたかということを。
エステルは、アベルにそっと抱き寄せられる。
薄い夜着ごしに感じるアベルの広い胸、腕をまわしても覆いきれない大きな背中。
アベルの存在。
ただそれだけを頼みに、この3年、ずっと気を張っていたらしい。
そうでなければ、解放されたようなこの安心感は説明がつかない。
止まらない涙のわけが判らない。
アベルは力を込めてエステルを抱きしめる。その腕も、震えていた。
言葉を超える想いの強さが、痛いほどに伝わってくる。
泣き崩れるエステルが落ち着いたのを見計らって、アベルは僅かに身体を離した。
もっとその胸に顔を埋めていたかったエステルは、小さく抵抗する。
もう二度と、離れたくなかったから。
けれどアベルは、強引とも思える仕草で抱きしめる腕をほどき、彼女の頭を大きな両手で包んだ。
頬を寄せてくるアベル。
一方的な勢いに、エステルは一瞬、ひるむ。
こんな身近で触れ合っていて、まして相手はアベルだ。エステルの気持ちが読めないわけではないはずなのに、けれどその想いは無視されてしまう。
アベルは僅かにあえぐエステルの唇を、ふさいだ。
優しいのは最初だけ。それは、猛烈なキスだった。
ほとばしる想いをぶつけるような、激しく狂おしく、むさぼるようなキス。
こんなキスをエステルは知らなかったし、アベルが知っていることが驚きでもあった。
なによりも、ほんの一瞬前までは怖ろしく思えたのに、触れ合った瞬間、激しさが幸せでたまらない。
キス、キス、キス。
唇に、まぶたに、耳元に、首筋に。
いつしかエステルは、アベルに組み敷かれていた。
アベルの手が夜着の内側に伸びようとする。
「 ――― 神父さま」
「は、ハイッ」
緊張にやや硬くなった口調に、素に戻って思わず手を引っ込めるあたりが、やはりアベルらしい。
エステルの頬がやわらぐ。
邪推して躊躇しているアベルの誤解を解かなければ。
「そうじゃなくて。 ――― おかえりなさい。神父さま」
「へ……?」
「おかえりなさいのキスをしたいって、わたし、申し上げたでしょう? だから。おかえりなさい、神父さま」
間近で、アベルの表情が無防備になり、みるみるうちにくしゃりと崩れた。まるで幼子のような顔だ。
アベルはそのまま、エステルに深いくちづけを落とした。
そうして再び夜着に取り掛かろうとするアベルに、声がかかる。
「あと、ね、 ――― 眼鏡が」
はぅ! とアベルは小さな声を洩らした。
あまりに間抜けたその声に、エステルは小さく笑う。
エステルの笑みに、アベルもおかしくなったのか、喉の奥で笑った。
片手でアベルは自分の眼鏡を外し、ぽんとナイトテーブルの上に放った。
|
|